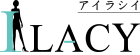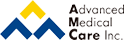減量外科医の大城崇司先生に聞く、「肥満症」を扱う肥満外来について【前編(全2回)】

「ダイエットを繰り返しても何度もリバウンドしてしまう」「健康診断で肥満症を指摘された」などの悩みを抱える人はいないでしょうか。
医療の現場では「肥満外来」への注目が高まっています。肥満症は糖尿病や不妊などにつながるリスクがあるうえ、自己流のダイエットでは解決できないケースが少なくはありません。
この課題を解決するのが、東京慈恵会医科大学の肥満外来(減量外科)です。
本記事では、肥満外来や肥満症の特徴、肥満と肥満症の違いなどを東京慈恵会医科大学の肥満外来(減量外科)で勤務する大城崇司先生からお聞きしました。次回の後編では具体的な肥満症の治療法などを紹介しますので、まずは前編で肥満症治療の全体像を把握しましょう。
東京慈恵会医科大学附属病院の肥満外来(減量外科)について
東京慈恵会医科大学附属病院における、肥満外来の概要や患者さんの傾向などをお聞きしました。
※本記事内での糖尿病は、すべて2型糖尿病となります
肥満外来に携わるきっかけと現在の役割をお聞かせください。
2006年当時、腹腔鏡手術が盛んな時期に腹腔鏡の手術を勉強するために東京の四谷メディカルキューブという病院に2年間勤務していました。
四谷メディカルキューブは現在も肥満症手術の中心的な施設で、腹腔鏡の手術を勉強しに行っていました。そこで私の師匠である「肥満症の手術を俺はやる、ここでやるために来たんだ」といって入職された笠間和典先生に出会いました。そこで行っていた肥満症治療のバイパス手術は体重減少だけでなく、糖尿病の患者の血糖値が翌日から劇的に改善するという効果がある結果に強い衝撃を受けました。
その後、東邦大学医療センター佐倉病院で15年間勤務し、がん手術なども含めた様々な経験を積みました。2010年からは本格的に肥満症手術を独り立ちして行うようになりました。
現在、日本では年間約900件の肥満症手術が行われていますが、韓国(約4000件)・台湾(3000件以上)・中国(約3万件)・インド(約1万件)などと比較すると非常に少ない数字です。この状況を改善するために、肥満症手術の普及に力を入れています。
普及が進まない理由として、肥満症手術を患者さんも知らないですし、内科の先生方は知っていても近くに減量外科医がいないなどが挙げられます。そのため、東京の中心部で肥満症治療に特化した診療を行うことを決意し、現在は肥満外来(減量外科)の責任者をしております。
肥満外来を受診される患者さんの傾向を、可能な範囲で教えてください。
外来受診の傾向は地域によって異なりますが、都会では女性の患者さんが多く、特に40代前後の方が多いようです。患者さんの主な悩みは「痩せたい」「綺麗になっておしゃれをしたい」「膝関節が痛い」「糖尿病が心配」など多岐にわたります。特に糖尿病に関する心配が多いようです。その他にも、高血圧、高コレステロール、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝などの関連健康障害も保険適用の対象となっていますが、これらを主な理由に手術を希望する方は少ないですね。
肥満と肥満症の違いとは
肥満と肥満症の違いや、肥満症を放置した場合のリスクなどをお聞きしました。
肥満と肥満症の違いについて、一般の方でもわかるように教えてください。
肥満と肥満症には明確な違いがあります。肥満は単に体内に過剰な脂肪、特に中性脂肪(トリグリセライド)が蓄積している状態を指し、必ずしも健康上の問題を引き起こすわけではありません。例えば、お相撲さんのように激しい運動をしている人は、肥満であっても必ずしも肥満症ではない場合があります。しかし、引退後に急激に健康状態が悪化するケースも多いです。
一方、肥満症は単なる脂肪の蓄積を超えて、その過剰な脂肪が健康に悪影響を及ぼしている状態を指します。
肥満症は医学的に治療が必要な病気として認識されています。肥満症には関連する11の健康障害があり、糖尿病・血圧・脂質異常・睡眠時無呼吸症候群や脂肪肝だけではなく、痛風の高尿酸血症・心臓の病気・脳梗塞・腎臓の病気・婦人科と月経異常などが含まれます。あとは、膝や股関節など整形疾患も大きな問題ですね。
これらの健康問題は、肥満症の治療や減量・代謝改善手術によって予防または改善できる可能性があります。例えば、早期に手術を受けることで糖尿病が寛解する方(検査値が正常で投薬がいらない)や腎機能が正常に戻る患者さんもいます。
肥満症の患者は、様々な健康問題を総合的に考慮し、適切な治療を受けることが重要です。減量・代謝改善手術は、健康問題の予防や改善に効果的な選択肢の一つとなります。
肥満症を放置した場合のリスクや合併症について、具体的に教えてください。
肥満症を放置することのリスクとして、糖尿病が悪くなれば透析になるかもしれませんし、目が見えなくなるかもしれません。脳梗塞などのリスクに心筋梗塞のリスクもありますし、いろんなことを放置することによって様々な問題が起きますよね。
例えば、腎臓病だって透析になるかもしれませんし、膝関節症では歩行に痛みを伴うことや、バランスが悪くなって転倒し骨折リスクもあるわけです。脂肪肝も、肝臓に脂肪がついてるだけと軽く思っている方も多いと思いますが、脂肪肝から、次は脂肪肝炎(B型肝炎やC型肝炎とは違った肝炎)の状態になり、それが進行すれば肝硬変や肝臓癌になる方もいます。
そのため、肥満症の治療のタイミングが重要です。早期に適切な治療を受けることで、多くの合併症の予防または改善が期待できます。
肥満症は女性特有の健康問題(妊娠、更年期など)に影響しますか?
不妊の原因は男性にもありますので男性・女性同時にペアで治療に取り組むがことが大前提です。その上で、肥満症は妊娠にも大きな影響を及ぼすことを理解しておくべきです。女性はホルモンバランスが崩れることで無排卵や月経不順を引き起こし、インスリン抵抗性が高まることで卵巣や子宮に悪影響を及ぼし卵子の質も低下します。
肥満症になるとインスリンが効きにくくなり(インスリン抵抗性)、そのためより多くのインスリンが出るようになります。インスリンは血糖値を下げてくれる体にとっても必要なホルモンですが、一方、インスリンは細胞を過剰に増殖させたりする作用もあるため、癌にもなりやすくなります。
女性だと卵巣癌や子宮体癌になりやすく、月経周期で言うと不順になりやすいので、妊娠するチャンスが落ちます。また肥満のある状態で妊娠すると、血圧が高くなることや妊娠糖尿病や流産も多くなります。経腟での出産は難しくなり帝王切開になる確率が高く、巨大児での出生だったり糖尿病を引き継ぐケースもあります。そのため、自身の体重を適正に管理することは将来の子供の健康にも良い影響を与えます。
また30代〜50代にかけての女性はエストロゲンの減少が進むため、体調や健康にさまざまな影響を及ぼします。エストロゲンは女性にとって非常に重要なホルモンで、若々しさを保つ働きを持っています。更年期になると、卵巣機能が低下しエストロゲンの分泌量が減少し、骨粗鬆症や血管の硬化などが進みやすく健康上の問題が増えます。特に40代前後から「急に体重が落ちなくなった」と感じる方も多いです。

更年期に向けては適切な体重管理を行うことが大切です。ただし「体重を落とせばいい」という単純な話ではなく、健康的で持続可能な方法で体重を管理する必要があります。更年期に入る前に、対策を行うことがおすすめです。特に食生活や運動習慣を見直し、適正な体重を維持することが健康への第一歩となります。また「今まで何を食べても大丈夫だった」ではなく、自身の体に合った生活スタイルを取り入れることも意識しましょう。
一般的なダイエットと肥満外来で受ける肥満症治療の違い
一般的なダイエットや肥満外来で受ける肥満症治療、美容目的のダイエットなど、それぞれの違いなどをお聞きしました。
一般的なダイエットと肥満外来で受ける肥満治療の違いを教えてください。
一般的なダイエット方法には、糖質制限や地中海食・リンゴダイエットなど様々な種類がありますが、万人に効果的な方法は存在しません。
ダイエットの効果は、個人の環境・食の好み・生まれなどの違いにより人それぞれです。医療機関での栄養指導を受けても必ずしも減量に成功するわけではなく、栄養士も継続できるよう個別化した治療提案を考えていますが、苦労している時もあります。
継続可能性の観点から、一時期流行したジムに通いながら栄養指導を受けダイエットを行うような極端な食事制限と運動を組み合わせた特殊な方法は継続が難しいと思います。
肥満症治療の特徴としては、食事療法や運動療法だけでなく薬物療法や外科的治療も選択肢に含まれます。脂肪吸引などの処置にも一定の効果を認めていますが、タイミングと施術してもらう医療機関の見極めをしてほしいです。
肥満症治療は、一般的なダイエットよりも多様な選択肢を提供し個別化されたアプローチを取りながら進めます。しかし患者の意思や生活環境・経済状況などの要因により成功の難しさがあることも事実です。
東京慈恵会医科大学附属病院の肥満外来(減量外科)では、どのような治療を行いますか?
肥満外来では、患者一人ひとりに合った治療法を提案するため内科的治療や外科的治療などの選択肢を提示し、患者の希望や状況を聞きながら進めていきます。いきなり手術を提案するのではなく、食事療法をしたことのない患者さんであればまずは専門の栄養士の話を聞いてみたり、薬物療法の経験がない患者さんには薬物療法を提案したりします。様々な治療をうけても十分な減量ができない時に、手術治療を考えます。
肥満症治療の中でも大切なのがメンタルの状況で、私達は必ず臨床心理士さんに介入してもらっています。問診票によるスクリーニングのみならず、臨床心理士さんによる面談を通すことによって、私たちが気づけなかったメンタルの不調を指摘してくれることもあります。例えば、「眠れない」「嫌なことを忘れようと食べるけど、それで嫌悪感が増す」、という発言から、何かおかしい、と感じ取って、その上で精神科医とも連携することで、状態が改善することも多く経験しています。メンタル治療も肥満症の治療アプローチの一つとなります。
肥満症治療と美容目的のダイエットの関係性を、どのようにお考えですか?
美容目的のダイエットは、適切に行われれば、個人的にはアリだと考えています。しかし、脂肪吸引などの外科的処置については、タイミングや医療機関の選択を間違わないようにしないといけません。皮下脂肪が厚い方に、不適切に脂肪吸引を行うと、出血もしやすく、また内臓損傷のリスクもあります。信頼のおける医療機関で治療を受けるのは重要なことです。
美容を謳うクリニックで受けた施術後のトラブルは、クリニックで解決できないことが多いですが、だからといってその対応ができる病院は限られていますし、またそもそも自費診療による美容施術後は保険診療を行う病院では対応してもらえないことがほとんどなので、本当に注意が必要だと思います。
もし脂肪吸引を受けたいのであれば、その前後で栄養指導を守れるのか、健康管理ができるのか確認した上でやるべきだと思います。食事で摂取した有り余ったカロリーはやがて脂肪に変わります。皮下脂肪を吸引しても、摂取カロリーが変わらない場合(もしくは消費カロリーが減らない場合)は、そのダブついたエネルギーは肝臓や内臓脂肪につくだけで、健康的になるわけではありません。単に見た目を良くするためだけのために脂肪吸引には飛びつくことは止めてほしいなと思います。
肥満治療についての【後編】はこちらからご覧ください
減量外科の大城崇司先生に聞く、「肥満症」を扱う肥満外来について【後編(全2回)】
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
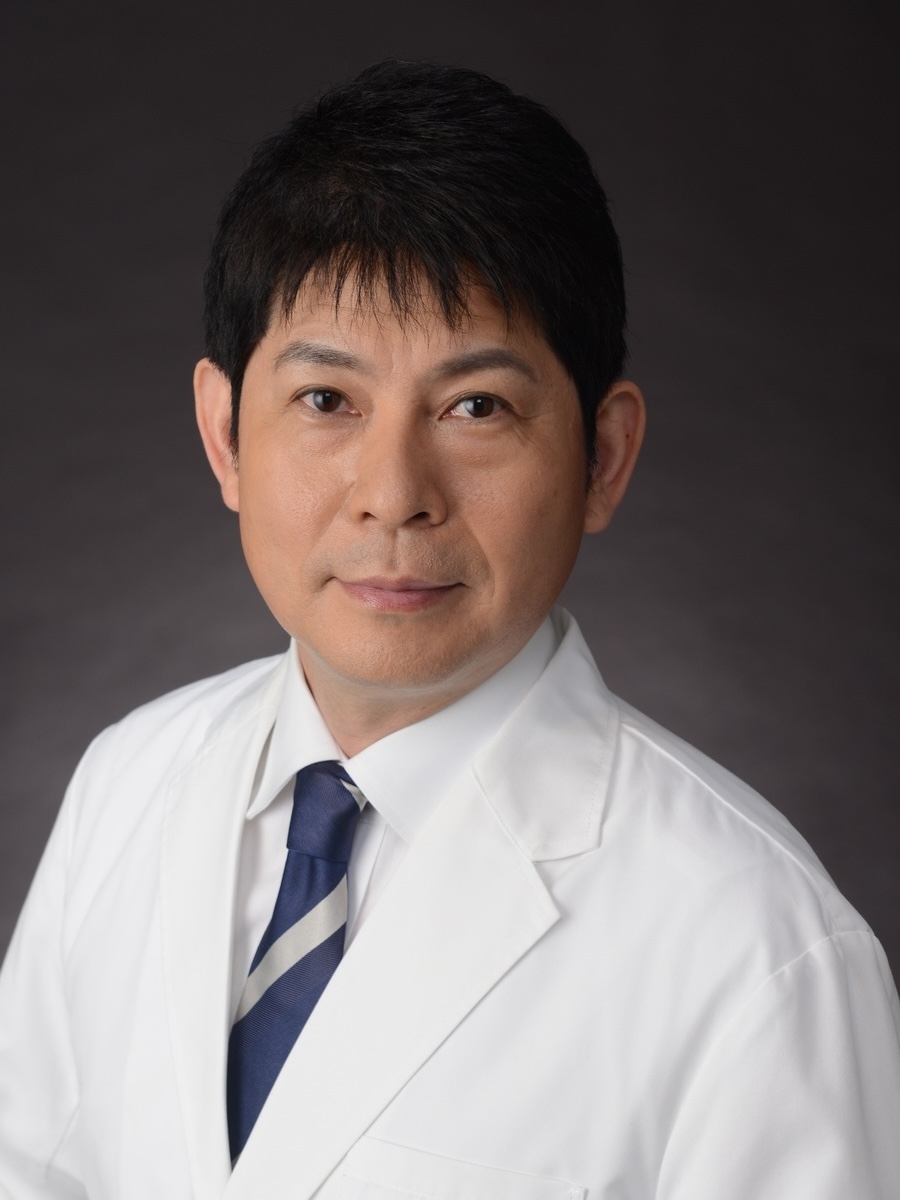
大城 崇司(おおしろ たかし)医師
医学博士
専門分野:上部消化管外科
1996年熊本大学医学部卒業。長崎医療センター、琉球大学医学部第一外科、四谷メディカルキューブ、東邦大学医学部外科学講座一般・消化器外科学分野を経て、2024より富山大学附属病院消化器・腫瘍・総合外科
客員教授兼任、2024東京慈恵会医科大学上部消化管外科 准教授、2025東邦大学医学部医学科 客員教授兼任となり、現在に至る。
2006年から減量・代謝改善手術に取り組み、国内有数の手術経験ならびに他施設での手術指導実績を有する。
日本外科学会専門医・指導医。日本消化器外科学会専門医・指導医。日本内視鏡外科技術認定医。日本がん治療認定医など。
アメブロ「肥満症治療を行う外科医のブログ」にて"ダイエットに必要な100の豆知識"を公開中。
https://ameblo.jp/shifuhana/
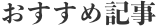 recommended
recommended
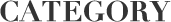 カテゴリー
カテゴリー