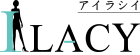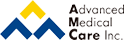減量外科医の大城崇司先生に聞く、「肥満症」を扱う肥満外来について【後編(全2回)】

「何度ダイエットをしてもリバウンドしてしまう」「健康診断でメタボリックシンドロームと指摘された」などのような悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。肥満症は単なる体重の問題ではなく、過剰な内臓脂肪が引き起こす病気です。
後編となる本記事では、前編で紹介した治療の全体像を踏まえ、具体的な手術事例と最新治療法に焦点を当てます。減量・代謝改善手術の術後経過から、GLP-1受容体作動薬の「ウゴービ」や、GIP/GLP-1受容体作動薬の「マンジャロ」 まで 、実例を交えて解説します。
また、東京慈恵会医科大学附属病院がどのようなチーム医療を行っているかについてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。
肥満外来(減量外科)で受ける肥満症治療の種類と特徴
肥満外来で受けられる肥満症治療について、具体的にお伺いしました。
※本記事内での糖尿病は、すべて2型糖尿病となります
肥満症治療の基本について教えていただけますか?
肥満症治療を受ける場合、手術という治療オプションがあることも知って、手術を受ける最適なタイミングを逃さないようにすることが重要です。
肥満症は慢性、進行性の病気であり、放置すると各臓器の機能低下(膵臓や腎機能の低下など)や身体の老化も進むため、適切なタイミングで手術を検討することが望ましいです。
内科治療で改善の余地がある場合は内科的アプローチを優先しますが、それでも効果が得られない場合は外科的治療も併用する方向で考えます。
内科的治療としては、具体的にどのような治療法がありますか?
具体的には最近はGLP-1受容体作動薬の「ウゴービ」や、GIP/GLP-1受容体作動薬の「マンジャロ」もありますね。ウゴービは糖尿病がなくても使えますが、マンジャロはGLP-1とGIPというホルモンの合剤で、これは糖尿病がないと日本では保険診療としては使えません(本記事執筆時点2025年3月)。またSGLT2阻害剤といって、尿から糖を出させて血糖を下げたり、体重を落とすお薬もあります。日本では、糖尿病があるなしで保険診療で使えるお薬が変わってきます。
今は、肥満症治療に使えるお薬が次から次へと出てきています。肥満症の治療では、ホルモンをコントロールすることも大切なポイントとなり、食べ物やお薬・手術でもホルモンをコントロールすることができます。ちなみに海外では、1番効くお薬になると、短期の減量効果がほとんど手術と変わらないものもあります。
内科的治療のデメリットとしては、現状、高度な肥満だけで糖尿病がない場合、お薬を使うまでのハードルが高い点です。糖尿病があれば体重減少を伴うお薬がすぐに使いやすいのですが、糖尿病のない肥満の患者さんに対しては、診療、栄養指導、運動療法の準備期間が必要で、それでも効果がない場合に初めて抗肥満薬の治療が検討されます。そもそも肥満症治療を専門にされている、良い内科医に出会うことが難しいのも問題です。
患者さんの中には健康的に薬物治療が始まるまでの半年が待てない状態の方もいますし、またお薬には吐き気や下痢・便秘などの副作用もあるため、約6割の患者が治療を途中で断念するとの報告もあります。
また、抗肥満症薬のウゴービでは投薬期間が68週までと決まっている点も問題です。決められた投与期間が終わると薬を一旦やめないといけないのですが、薬物治療ををやめると必ずリバウンドしますし、そもそもお薬がとても効く人もいれば、ほとんど効果がない人もいます。お薬が効きにくい方もも10%〜15%くらいいると言われています。
また最近では胃カメラで胃を小さくする内視鏡的スリーブ状胃形成術という方法もあります。東京慈恵会医科大学附属病院(内視鏡学講座)では、特定臨床研究の自費診療として行われていますが、全国的にみても普及しているとは言えず、3施設のみに留まっており、これからの治療と言えます。
外科手術としては、どのような治療法がありますか?
将来的には、皆さんがお薬を1粒飲むだけで太らずに、糖尿病もなくなるような薬ができると良いと思っていますが、まだ現実的には難しいので、現時点ではやはり安全性や長期的な効果のエビデンスのある減量・代謝改善手術が必要だと思います。ちなみに、ネガティブな単語を含む肥満手術という呼び方ではなく、ポジティブな言葉を含む減量・代謝改善手術という呼び名が正式です。
減量・代謝改善手術は、全例腹腔鏡で行い、長期的な減量・代謝改善効果が期待できます。みなさんは手術と聞くと敷居を高く感じるかもしれませんが、侵襲性の面から言えば、術後3~4日日で退院することもできる、消化管手術の中でも安全な手術の一つと言えます。傷に関しては、0.5㎝から1cm程度の切開で、5~6カ所に孔を開けて行う手術で、大きな傷は伴いません。
手術のデメリットとしては、出血や縫合不全のリスクなどがあります。保険診療による手術では胃を切除して細くしますので、通過障害や逆流性食道炎(症状としては胸焼けなど)を来す方もいます。また栄養障害も起こりうるため、長期的にその評価も行う必要があります。
手術療法の具体的な手術方法とその特徴を教えてください。
肥満症治療においては、内科的治療、メンタルケアを含めた包括的なアプローチが重要です。外科療法もその一つの選択肢として提供されています。
- 1.スリーブ手術
- 胃を7割切除してバナナ状にし、食事摂取量を制限します。
- 胃容量は約100cc(一般的な栄養ドリンク程度)となり、食欲を促すホルモン「グレリン」の分泌が減少するため、食欲が抑えられ、穏やかになります。
- 食事が腸の下部まで早く到達することでGLP-1ホルモンが分泌され、薬剤を使用しているような効果も得られます。
- 保険診療です。
- 2.スリーブバイパス手術
- スリーブ手術に加えて十二指腸と上部空腸に食物を通さないように消化管の解剖構造を変化させた手術です。
- 血糖コントロールや長期的な体重減少に効果的であり、2024年6月から保険適用となりました(BMI35以上かつ糖尿病患者が対象)。
- 十二指腸切離を伴わない安全性が高いスリーブバイパスも行われるようになっており、当院(東京慈恵会医科大学附属病院)では「スリーブバイパーティション」という手術を実施しています。
- 3.ルーワイバイパス手術
- 世界でも行われている胃を残せる手術ですが、日本では保険診療では行えません。当院では今後自費診療として提供する予定です。
- 元大関の小錦さんや、サッカー選手のマラドーナも受けた手術法です。
当院では、患者さんの状況や希望に応じて最適な治療法を提案しています。「効果」「持続性」「費用」などの要素について十分な説明を行ったうえで、患者さん自身が納得して選択できるようサポートしています。多様なアプローチから患者一人ひとりに合った最適な治療法を提供することが肥満症外来の特徴です。
※手術の詳細は、大城崇司医師の運営するHP「東京慈恵医科大学付属病院
減量外科jikeidiet.com」も参考にしてください。HPはこちら
各治療法の費用や保険適用の状況について、大まかな範囲で教えてください。
日本では高額療養費制度を利用することで、手術費用は約10万円程度で済むため世界的に見ても非常に安価といえます。ただし、内視鏡胃形成術は自費診療のため約130万円程度かかります(2025年3月現在)。
一方で薬物治療の場合、例えばGLP-1製剤の「ウゴービ」を最大量使用すると、保険診療であっても月々約2万円の費用がかかり、他の薬剤も併用すると月3万円〜4万円程度必要になることがあります。このような薬物治療は一生続ける必要があるため、経済的な負担が大きいことが課題です。
東京慈恵会医科大学附属病院の肥満外来(減量外科)のチーム医療
肥満外来のチーム医療や具体的な栄養指導についてお聞きしました。
「肥満症患者さんに寄り添ったチーム医療」とは、どのような体制ですか?
コアメンバーは内科医(糖尿病・代謝・内分泌専門)・外科医・栄養士・臨床心理士で構成され、さらに負担の少ない麻酔をかけるための専属の麻酔科医もいます。心臓の悪い患者さんでしたら循環器内科医、腎臓の悪い患者さんには腎臓内科医といった各専門の先生たちがサポートについてくれます。
チーム医療の利点として、各専門家が患者さんの状況に応じて適切な対応ができることが挙げられます。例えば、医師が十分な時間を取れない場合でも、栄養士が詳細に話しを聞き取り、その情報をチーム皆で共有し、患者さんにとってより良い医療を提供することが可能となります。
また「DOCEO(ドケオ)」というアプリを導入し、患者同士のサポートコミュニティを構築しています。このアプリを通じて患者の声を聞いたり、定期的な患者会のチャット開催(今後はZOOM開催も企画する予定)や手術に関する質問に回答したりしています。今後は仮想空間での交流も考えています。
栄養指導や運動療法の内容について詳しく教えてください。
栄養指導は、単に食事内容を指示するだけでなく、患者の話を丁寧に聞き、寄り添うことが重要です。日本の栄養士さんはプロ意識が高く、非常に真面目で優しい傾向があり、患者にとって癒しの場となることもあると感じています。最も効果的な栄養指導は、患者が継続できるものにすることです。
運動療法では、理想的には有酸素運動とレジスタンス運動(筋肉に負荷をかける運動)を組み合わせることが推奨されますが、実践は難しい場合があります。まずは歩くことから始めるようすすめています。スマートフォンのアプリなどを活用して、歩数を管理することも有効です。運動療法も栄養指導同様、継続が鍵となります。フェイス・トゥ・フェイスでの指導や励ましが効果的で、患者さんの努力を認め共感することが重要です。

肥満症治療における手術の適応条件
肥満治療の手術の適応条件(BMIや年齢など)を詳しくお聞きしました。
減量・代謝改善手術の対象となる条件について教えてください。
BMI32以上の高度肥満がある方に手術の適応があります。(目安は身長160cmで体重82kg以上、身長170cmで体重93kg以上)。ただし、体重だけで手術適応が決定されるわけではなく、その他の肥満関連健康障害(糖尿病、脂質異常症、高血圧症、睡眠時無呼吸、脂肪肝)を有することも条件になるため、詳細は私が運営するjikeidiet.comや手術を実際に行っている病院のホーページも参考にしてください。
保険診療による手術適応には、年齢制限はそもそもありませんでしたが、2024年に日本肥満症治療学会から刊行された「減量・代謝改善手術のための包括的な肥満症治療ガイドライン2024」では、年齢は13歳以上とし、上限は設けていません。高齢者でも、手術から多いにメリットが得られる場合もあります。
良いタイミングで、適切な治療を受けることでメリットが大きく得られます。肥満症治療には多彩な選択肢がありますので、自身の状況に合った方法を担当医と相談しながら検討していくことが大切です。
13歳以上の未成年者に対する肥満症治療で特に考慮すべき点はありますか?
小児肥満の治療オプションは限られており、薬物治療も適用外となることが多いため、認知行動療法などのアプローチが主流です。しかし、重度の肥満ケースではこれらの方法だけでは残念ながら効果は限定的です。
個人的には、内科的治療抵抗性であった14歳(170kg)の患者さんに手術を行った経験があります。小児肥満は低身長の原因になるため早期介入が重要ですが、本人の理解力や意思決定の問題が常にありますので、中学から高校への移行期(トランジション期)に手術を検討することが有効だと考えています。この時期に適切な介入を行うことで、いじめや不登校などの社会的問題を緩和し、小児肥満の患者さんの人生を大きく変える可能性さえあります。
ただし、小児への手術適用には本人の理解と同意、家庭環境の評価、保護者の協力など、多くの要因を慎重に検討する必要があります。患者本人が十分に納得した上で治療を進めることが重要です。
肥満外来で注目される最新の治療法と薬物療法
肥満症治療における最新の治療方法や、美容目的で医療ダイエットをする若年層についてお聞きしました。
肥満症治療の最新の治療法や注目されている薬剤があれば教えてください。
マンジャロと同じ成分であるゼップバウンドが国内でも今後、保険診療として使えるようになり、また海外では様々なホルモンの組み合わせによる薬剤が次々と開発され、これから市場に投入されてくるはずです。これらの薬剤は、ダイエットに役立つホルモンを味方にすることで効果を発揮します。
また、特にバイパス系の手術も、体にとって有益なホルモンを増強させる効果が期待できます。ホルモンを味方にする方法として、薬物療法と手術療法、またそのコンビネーションによる治療のどれも有効だと考えています。
オゼンピックやマンジャロなどのGLP-1受容体作動薬(糖尿病治療薬)が美容目的で使用されることについて、医療の立場からどのようにお考えですか?
例えばBMI22の方が、BMI20を切るために受けたい場合などは治療ではありません。それはダメです。
新薬の開発と供給は今後も増加すると予想されますが、不適切な使用や若年層への影響など、社会的な懸念も存在します。薬物による過剰な体重減少は、将来のリバウンドや健康障害を高めるリスクがあるため、決して許容されるものではありません。しかしながら、保険適応のない程度の肥満で悩んでいる方も多くいるのは事実で、今後はそのような方を対象に、専門家の監督下での自費診療による「メディカルダイエット」も提供されていくのではないかと考えています。
脂肪吸引や脂肪溶解注射、脂肪冷却痩身など、若い人たちが美容目的で医療ダイエットを利用する機会が増加しています。このことについて、どのようにお考えでしょうか?
美しくなりたいという気持ちは否定しませんし、むしろ応援しています。美容整形や脂肪吸引などの治療については、費用だけで安易に決定してほしくはありません。食事・運動を基本として生活習慣を見直し、十分な準備をした上で、信頼のおける施設で、専門の先生とよく相談をした上で、施術を受けるようにしてほしいと思います。
東京慈恵会医科大学附属病院における肥満外来(減量外科)の術後のケアと生活の変化
手術後の回復期間や食事制限、再発のリスクなどをお聞きしました。
手術後の回復期間や、患者さんの生活の変化を教えてください。
手術に必要な入院期間は通常3〜4日程度です。手術当日は最大限の安全を考慮して集中治療室(ICU)で1泊し、万全の体制で経過観察を行うようにしています。翌日から一般病棟に移り食事も歩行も開始します。術後の食事はスープから始め、徐々に柔らかい食事に移行し、約1ヶ月後に通常の食事形態に近づきます(当然食べられる量は手術前に比べてかなり少なくなります)。この期間は、ゆっくりと少量ずつ食べる習慣を身につける「食べ方のリセット期間」と考えられています。

術後の食事制限や運動療法について、アドバイスはありますか?
術後は食べられる量が極端に少なくなるため、何を優先的に食べるかが大事です。具体的には糖質や間食は控えめにして、タンパク質と食物繊維の摂取をおすすめしています。水分摂取ではジュースやスポーツドリンクは避け、水やお茶を中心に1日2リットルを目標としますが、最低でも1リットルは摂取するように指導しています。
運動療法は継続的に行うことが重要です。そのため、急激な運動ではなくウォーキングから始め、徐々に距離を伸ばしていくことをおすすめします。可能ならば食後20〜30分以内に体を動かすこともコツの一つです。また、プールでの歩行は関節にも優しく効果的ですので、患者さんの好みや状況に応じて選択するとよいでしょう。
治療の長期的な効果や再発のリスクについて教えてください。
効果は人それぞれですが、体重の20〜30%程度の減量も期待できます。肥満に関連する健康障害の改善も見込まれますが、長期的に効果を維持するには継続的な管理が必要だと考えています。
術後もリバウンドとの闘いは続きます。体重が増えれば、手術前と同じ問題に直面します。リバウンド防止のため、内科医、栄養士などとのチーム医療が大事ですし、手術後もかかりつけ医との連携や定期的なフォローアップを通じて、長期的な健康管理を行う必要があります。
手術を受けたからと言って、肥満に関連する全ての問題が解決するわけではありません。手術は新しい人生を送るための、きっかけにしかすぎないことを理解して、上手く活用してほしいと思っています。
肥満症治療の成功例と患者に起きる心理面の変化
肥満症治療の成功例や、治療の過程における患者さんの心理的な変化などをお聞きしました。
実際に治療を受けて成功した患者さんの例を、教えていただけますか?
手術の成功例には、体重が落ちて見た目にも若々しく魅力的になることもありますし、糖尿病が改善する方も多くいらっしゃいます(検査値が正常で、お薬も不要)。また不妊治療を行っていた方が子供を授かるケースも経験しています。
肥満には遺伝的要因が約70%関与していると言われています。手術によってこの遺伝的影響が次世代に引き継がれにくくなる可能性があるため、子供のためにも肥満のある親が手術を受けることも治療選択肢としては大切だと考えています。
治療過程の患者さんの心理的な変化や、それに対するサポート方法は?
肥満症の患者さんの方には「うつ」の方も多いです。肥満があるから「うつ」になるし、「うつ」があるから肥満にもなるとも言われています。手術の結果によっては気分も晴れる人もいますし、思った結果ではないことや取り巻く社会環境が変わらないことから、「うつ」が改善されない患者さんもいらっしゃいます。
つまり「手術したからといってすべての心の問題が解決することはない」ということです。だからこそ、メンタルのスクリーニングや心理士によるインタビューを通じて、場合によってはメンタル面の治療にアクセスすることも考えてあげないと、治療がうまく進みません。
当院(東京慈恵会医科大学附属病院)では、術前から心理士や精神科医の介入を積極的に行っています。術後も多職種で患者さんをサポートしていくわけですが、その過程でメンタルの異変を感じたら、どの立場の者からでも心理士に相談して、必要に応じてメンタルの治療を行えるようにしています。手術を含め肥満症の治療では、互いにサポートできるチーム医療体制を作ることが重要なポイントです。
肥満症の予防と日常生活のアドバイス
肥満症予防の観点から、日常生活で意識したほうがよい点や食事・運動などについてアドバイスをもらいました。
肥満症を予防するために、日常生活で気をつけるべきことは何でしょうか。
肥満症治療において食事と運動のタイミングが大切です。特に、食事の内容や食べるタイミング、食べるスピード、また運動(歩く)のタイミングに注意を払う必要があります。
わたし自身の「肥満症治療を行う外科医のブログ」で、ダイエットに関する100以上のコツを紹介しています。このブログは「アメブロ 大城崇司」で検索することで閲覧可能で、血糖変動や糖質制限に関する具体的な情報も掲載されています。
外来で患者に伝えている内容をブログにまとめていて、毎日1記事ずつ100日間にわたって投稿しましたので、読んでいただくと参考になると思います。
※大城崇司医師の「肥満症治療を行う外科医のブログ」はこちら
健康的な体重管理のために、食事や運動についてアドバイスをお願いします。
肥満症治療において、レコーディングダイエット(食事内容や体重などを記録する)は有効です。気分の乗らない日もあると思いますが、体重やどのような物を食べたのか、どれぐらい歩いたのか記録をつけて振り返ってみて下さい。その振り返りを通して、体重が落ちている時の食事や歩数を意識してみてください。ウェアラブルデバイスの活用も有効だと思いますので、自分に合ったデバイスを選択して、ダイエットに、健康に、役立てると良いと思います。
読者の皆様へメッセージ
最後に、大城崇司医師から読者の皆様へメッセージをいただきました。
肥満症で悩んでいる方や、肥満外来(減量外科)の受診を迷っている方へ。
治療を受ける年齢の上限はありませんが、もし肥満で体重が落とせずに悩んでいらっしゃる方がいれば、早い段階で近隣の肥満外来を受診することをおすすめします。受診が早い方が治療から受けられるメリットが多くなります。
肥満症の治療は長期的な健康上のメリットが大きく、肥満が要因で起こる疾患を予防することで、医療費の削減や健康寿命の延長も期待できますので、前向きに取り組んでいただければと思います。
当院(東京慈恵会医科大学附属病院)では肥満外来(減量外科)が窓口になっていますが、高度肥満(BMI32以上が目安)でお困りの方がいらっしゃいましたら、かかりつけ医からの紹介状をお持ちになって、まずは治療選択肢のお話しだけでも聞きにいらしてください。何か良い解決策が見つかるはずです。
肥満治療についての【前編】はこちらからご覧ください
減量外科の大城崇司先生に聞く、「肥満症」を扱う肥満外来について【前編(全2回)】
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
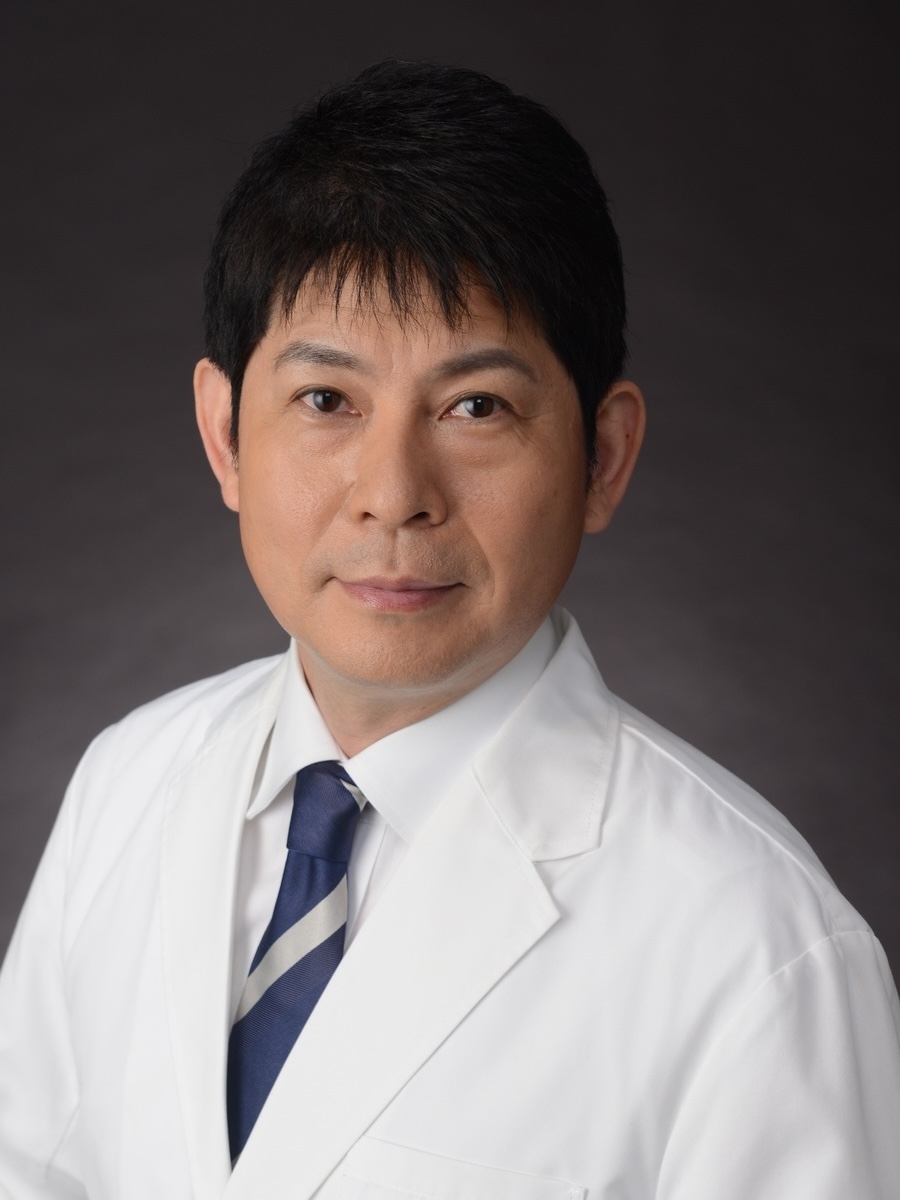
大城 崇司(おおしろ たかし)医師
医学博士
専門分野:上部消化管外科
1996年熊本大学医学部卒業。長崎医療センター、琉球大学医学部第一外科、四谷メディカルキューブ、東邦大学医学部外科学講座一般・消化器外科学分野を経て、2024より富山大学附属病院消化器・腫瘍・総合外科
客員教授兼任、2024東京慈恵会医科大学上部消化管外科 准教授、2025東邦大学医学部医学科 客員教授兼任となり、現在に至る。
2006年から減量・代謝改善手術に取り組み、国内有数の手術経験ならびに他施設での手術指導実績を有する。
日本外科学会専門医・指導医。日本消化器外科学会専門医・指導医。日本内視鏡外科技術認定医。日本がん治療認定医など。
アメブロ「肥満症治療を行う外科医のブログ」にて"ダイエットに必要な100の豆知識"を公開中。
https://ameblo.jp/shifuhana/
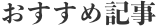 recommended
recommended
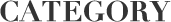 カテゴリー
カテゴリー