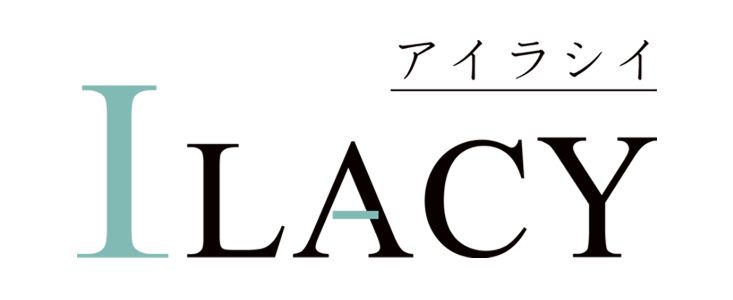【医師監修】膵臓がんはなぜ見つけにくい?検査・治療・予防の最前線
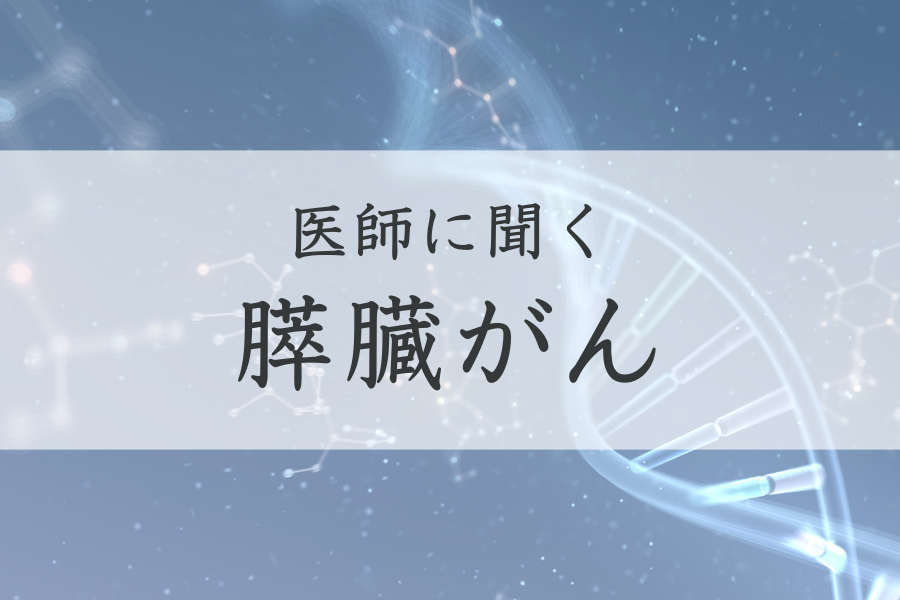
膵臓がんは「早期発見が難しいがん」として知られています。 膵臓は体の中心部にあるため、症状が出にくく、検査でも見つかりにくいという厄介な特徴があります。そのため、診断された時にはすでに進行しているケースが少なくありません。それでも、血糖値の異常や黄疸といったサインをきっかけに、早期に気づける可能性もあります。 さらに近年では遺伝子検査や新しい抗がん剤治療の進歩により、治療の選択肢が広がりつつあります。また生活習慣の改善がリスク低減につながることも明らかになってきました。
今回は、日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニックの大久保栄高医師に、膵臓がんの特徴や最新の医療、そして日常生活でできる予防のヒントについて伺いました。
膵臓がんの初期症状や、患者さんが気づきやすいサイン、見逃しやすいサイン、自覚症状にはどのようなものがありますか?
膵臓がんも、肝臓がんと同様に初期にはほとんど症状が出ません。 腰痛や背中の痛み、黄疸(特に膵臓の頭の部分に腫瘍ができて胆管が圧迫される場合)、急な体重減少や食欲不振といった症状が出ることもありますが、必ずしも「がんを疑う決め手」にはなりません。
早期の状態で黄疸(皮膚や白目が黄色くなる症状)が出て診断できるケースもありますが、腫瘍の場所や大きさによってタイミングはさまざまです。「なんとなく体調が良くない」「腹痛やだるさが続く」などの不明確な症状が続き、検査により初めて診断されるケースもあります。
膵臓がんは早期発見が難しいと言われていますが、どのような検査方法や研究が進められているのですか?
膵臓は体の奥深くにあるため、通常の内視鏡検査では直接観察することができません。またCTや超音波などの画像検査でも1cmほどの小さな膵臓がんは見つけにくいと言われています。
進化する膵臓がんの検査法と、定期検診の重要性

血液検査で測定できる腫瘍マーカーの「CA19-9」は、膵臓がんの方では上昇することがありますが、健康診断のように元気な人を対象とした検査では「偽陽性(本当はがんでないのに数値が高い)」
が多く、正確性に限界があります。
そこで近年は、より正確に膵臓がんを見つけられる新しい血液検査の研究が進んでいます。たとえば、「リキッドバイオプシー」という血液中の遺伝子(RNAなど)を調べる方法と腫瘍マーカー(CA19-9)を組み合わせる検査では、有効性を示す海外の報告も出ています。まだ研究段階ですが、将来の実用化が期待されています。
また、特に膵臓がんのリスクが高い方(家族に膵臓がんの人がいる方、慢性膵炎がある方、新しく糖尿病と診断された方など)では、MRIや超音波などの検査を定期的に受けることで早期発見につながるといわれています。
膵臓がんは「早期発見が難しいがん」ではありますが、新しい検査法の進歩やリスクの高い方への定期的な検査によって、早期発見の可能性を高める取り組みが進められています。
膵臓がんの主なリスク要因について教えてください
膵臓がんのリスク要因① 慢性膵炎
膵臓がんの主なリスク要因のひとつは慢性膵炎です。慢性膵炎は長い間お酒をたくさん飲むことで起こりやすく、膵臓に石ができたり(膵石)、膵臓の機能が弱ってしまったりします(萎縮)。 その他に肥満や中性脂肪の高値も関係していますが、それだけでがんになるわけではなく、体質的な要因や食生活・お酒の飲みすぎが重なる場合にリスクが増加します。
膵臓がんのリスク要因② 喫煙
喫煙もとても重要で、飲酒以上に関連が強いという報告もあります。また二親等以内に2人の膵臓がん患者がいると「遺伝性膵がん症候群」と定義されます。つまり、家族歴がある方は通常よりも膵臓がんのリスクが高いとされています。 また、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)と呼ばれる腫瘍が膵臓にできた場合も発がんリスクが上がります。
こうしたリスクがある方では、MRIや超音波内視鏡で定期的に検査することが勧められます。ただし、注意深く検査しても早期に見つかるのは半分程度で、多くは進行してから診断されるのが現状です。
診断時に多いステージや、発見が遅れやすい理由は何ですか?
膵臓がんは見つかった時にはおよそ8割がステージ3や4と進行した状態で、初期のステージ1で見つかることはまれです。
 発見が遅れやすいのはいくつかの理由が重なるためです。膵臓はお腹の奥にあるため、内視鏡で直接観察することができず、小さな病変はCTや超音波検査でも発見が難しい臓器です。さらに、初期には自覚症状がほとんどなく、症状が現れるのは、がんが進行してからという特徴があります。
加えて、胃がんに対する胃カメラや大腸がんに対する大腸内視鏡、肺がんに対する胸部CTのような、一般の人を対象とした有効な検診方法が膵がんにはまだありません。
発見が遅れやすいのはいくつかの理由が重なるためです。膵臓はお腹の奥にあるため、内視鏡で直接観察することができず、小さな病変はCTや超音波検査でも発見が難しい臓器です。さらに、初期には自覚症状がほとんどなく、症状が現れるのは、がんが進行してからという特徴があります。
加えて、胃がんに対する胃カメラや大腸がんに対する大腸内視鏡、肺がんに対する胸部CTのような、一般の人を対象とした有効な検診方法が膵がんにはまだありません。こうした要因が重なり、膵臓がんは他のがんと比べても特に早期発見が難しいとされています。
膵臓がん治療の基本方針について教えてください
膵臓がんの治療は肝臓がんとは異なり、ラジオ波焼灼術のような治療法は使いません。基本的には外科手術で腫瘍を取り切ることが最も有効な治療です。ただし、早期の段階で診断・切除ができる方は少なく、約8割は手術ができないのが現状です。
手術が難しい場合は抗がん剤による化学療法や放射線治療を組み合わせて腫瘍を小さくし、改めて手術が可能かどうか検討することもあります。ただし、膵臓がんは特殊な構造(線維性被膜や血流の乏しさ)をもっており、抗がん剤が効きづらいという課題があります。
膵臓がん治療のための放射線治療や化学療法の特徴や、メリット・デメリットにはどのようなものがありますか?
抗がん剤治療のメリット・デメリット
抗がん剤(化学療法)は全身に作用するため、膵臓から他の臓器に広がったがんにも効果を期待でき、生存期間を延ばすことが証明されています。ただし、膵臓は薬が届きにくい特徴があるため効果が十分でないこともあり、吐き気や下痢、だるさ、血液検査の異常など副作用が出やすい点が課題です。
放射線治療のメリット・デメリット
放射線治療は、がんが膵臓の周囲に広がって手術できない場合に使われ、抗がん剤と組み合わせることで進行を抑えたり、痛みを和らげたりする効果がありますが、胃や腸に負担がかかって下痢や食欲不振などの副作用が出ることもあります。
いずれの治療も完治を目指すのは難しいことが多いですが、がんの進行をできるだけ抑え、生活の質を保ちながら少しでも長く過ごせるようにすることが大きな目的となっています。
膵臓がんの新しい治療法はありますか?
膵臓がんに対しても、免疫の働きを利用する新しい薬(免疫チェックポイント阻害薬)や、患者さん自身の免疫細胞を遺伝子操作で強化してがんを攻撃させる治療(CAR-T療法)といった先進的な治療法に期待が集まっています。
しかし、現時点ではこれらの方法で根治できるケースは限られており、膵臓がんの治療は依然として難しいのが現実です。そのため、病気の進行度や体の状態、ご本人やご家族の希望を踏まえて、最適な治療方針を一緒に相談して決めていくことが大切です。
膵臓がんを防ぐために日常生活でできることはありますか?
膵臓がんには、残念ながら確立された予防法はありません 。しかし、いくつかの生活習慣がリスクを高めることは分かっています。代表的なのは喫煙や過度の飲酒、そして糖尿病や肥満など生活習慣病との関連です。
膵臓がんの予防には禁煙が重要

禁煙は膵臓がん予防の観点から最も重要で、喫煙者は非喫煙者に比べて明らかにリスクが高いとされています。 また、糖尿病や脂肪肝のある方は膵臓に慢性的な負担がかかりやすく、バランスの良い食事や適度な運動がリスク低減につながります。
膵臓は不調があっても症状が出にくいため、日常生活でできる工夫は「膵臓に余計な負担をかけない」ことに尽きます。特に喫煙習慣のある方や糖尿病を抱える方は、生活習慣を整えることが予防の第一歩になります。
定期的な膵臓がんの検診は受けた方がいいですか?
現在のところ、膵臓がんについては「全員が定期的に検診を受ければ早期発見できる」という状況にはなっていません。 なぜなら、膵臓は胃や腸の奥に隠れており、一般的な健康診断の超音波検査では十分に観察できない場合があるからです。また、血液検査でも早期の膵臓がんを見つけるのは難しいとされています。
膵臓がんの発見には、喫煙者と家族歴がある方の医師への相談が重要
一方で、膵臓がんのリスクが高いとされる人については、より詳しい画像検査(CTやMRI、内視鏡超音波検査など)を医師と相談しながら受けることが勧められます。
膵臓がんのリスクが高いとされる人は、喫煙者や膵臓がんの家族歴がある方、糖尿病が急に悪化した方、慢性膵炎の方などが当てはまります。つまり、膵臓がん検診は「誰でも定期的に受けるべき」というよりは、リスクを持っている方が重点的にチェックを受けるという考え方になります。
自分がその対象になるかどうか、まずはかかりつけの医師に相談してみるのが安心です。
膵臓がんと向き合うために、今からできること
膵臓がんは、残念ながら今の医療でも早期に見つけるのが難しい病気です。だからこそ大切なのは「リスクをできるだけ減らすこと」と「体の小さな変化に気づくこと 」です。
禁煙する、生活習慣病をきちんと管理する、そして「何かおかしい」と思ったときに放置せず受診する。その積み重ねが、早期発見や治療の可能性につながります。
「自分は大丈夫」と思ってしまいがちですが、膵臓がんは誰にでも起こりうる病気です。気になることがあれば、一人で抱え込まずに、かかりつけ医や専門医に相談してください。
医療者と一緒に向き合うことで、できることは必ず見えてきます。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人

大久保 栄高(おおくぼ ひでたか)医師
専門分野:消化器内科
日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック院長補佐。
日本内科学会 総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医。
日本消化器病学会 消化器病専門医。日本肝臓学会 肝臓専門医。
日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック:https://www.mtc-nihonbashi.jp
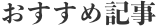 recommended
recommended
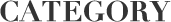 カテゴリー
カテゴリー