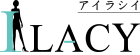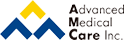夏冷えとは、どのような状態?原因と対策方法を解説

夏といえば、近年は熱中症の危険性が全国各地で叫ばれるほど、とにかく暑い季節。ですが、夏にもかかわらず、体が冷えて調子を崩してしまうことがあります。
夏といえば、近年は熱中症の危険性が全国各地で叫ばれるほど、とにかく暑い季節。ですが、夏にもかかわらず、体が冷えて調子を崩してしまうことがあります。
本記事では、暑い夏に体が冷えてしまう"夏冷え"とよばれる状態について、どうして冷えてしまうのかの説明とともに、対策方法を解説します。
夏冷えとは?
まず"夏冷え"は、医学用語ではなく、世間一般で概念的に使われている言葉です。そのため、「医学的に、このような状態を夏冷えという」といった定義が決められているわけではありません。
一般的には、以下いずれかの状態を指して"夏冷え"とよぶことが多いようです。
【夏冷えの一般的な定義】
- 冷房に当たって体が冷えている
- 冷たいものを食べて内臓が冷えている
- 自律神経の乱れによって冷えを感じる
夏冷えの原因
夏冷えとよばれる状態には、いくつかの原因があります。原因を把握して、適切に対策していきましょう。
冷房
猛暑から身を守り、快適に過ごすためには欠かせない冷房ですが、当たりすぎると"涼しくて心地良い"を通り越して、体を冷やしてしまいます。
また、冷やしすぎだけでなく、室内外の気温差にも注意しましょう。気温差が大きいと体がストレスを感じ、体温を一定に保とうとする自律神経が乱れてしまうことがあります。その結果、体の疲れや食欲不振といった、いわゆる"夏バテ"につながります。
冷たい飲食物
体の外側だけでなく、内側からの冷えにも気を付けましょう。冷たい飲み物や料理、アイスなどは夏の醍醐味ですが、冷たい飲食物をとりすぎると体の中が冷えてしまいます。
冷たい飲食物がもたらす影響は体の冷えだけではありません。冷たいものをとると、まず胃が冷え、それによって消化・吸収を助ける"消化酵素"のはたらきが弱くなります。そこから食欲不振をはじめとする体調不良にもつながる可能性があるのです。
そして、臓器は動くことにより一定の熱を発しますが、動かなくなると冷えます。胃の動きが低下することで、さらに内側から体が冷えるおそれもでてきます。
女性の場合は、月経痛への影響にも気を付けたいところです。体が冷えると血の巡りが滞ります。月経のときに血の巡りが滞ると、体質によっては月経痛を感じることがあります。
冷たいものは一度に大量に食べたり飲んだりせず、体の調子と相談しながら、少しずつとるよう意識しましょう。
筋肉量
筋肉は「熱を作る臓器」ともいわれています。そのため、筋肉量が少ないと夏であっても体が冷えやすくなります。
特にデスクワークなど、日常的に体を動かす機会があまりない方は要注意です。筋肉は動かさないとどうしても量が少なくなってしまいます。筋肉量が落ちると血の巡りも悪くなるので、体の冷えにつながります。
女性の場合は男性よりも筋肉量が少ないので、体が冷えやすい傾向にあります。そして筋肉は年齢とともに落ちていくので、更年期の女性で体の冷えが気になる方は、筋肉量に原因があるかもしれません。
夏冷えの対策におすすめの生活習慣
夏冷えは、冷房といった外的要因と、体の仕組みの両方が原因となりえることがわかりました。ここからは、上記でお伝えした夏冷えの原因を踏まえ、対策方法をお伝えします。
生活編
まずは、日々の生活で意識できる対策方法です。
温度調節に気を付ける
冷房のきいた部屋で過ごすときは、適切な温度に設定して、体を冷やしすぎない程度にとどめましょう。
オフィスなど、ご自身で温度の設定が難しい場所で長時間過ごす場合は、上着を羽織って体温調節するなどして、体に負担を与えないことが大切です。暑い室外と冷房のきいた室内を行き来する場合も同様に調節し、急激な温度変化を体に感じさせないよう意識してみてください。
冷房による冷やしすぎを防ぐポイントについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
夏の体調管理は「冷房病対策」がカギ!初夏から実践したい予防法
お風呂で温まる

お風呂で一日の汗を流すとともに、体を温めるのも一案です。
「ただでさえ暑いのに、お風呂なんて......」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、湯船に浸かって全身を温めることで血行が促進されるので、筋肉不足などによる血行不良が原因で体が冷えやすい方には、ぜひ試していただきたい方法です。シャワーでサッと済ませるのもいいですが、夏だからこそ、たまにはバスタイムを楽しんでみませんか?
夜にお風呂に入ると入眠しやすくなる傾向もあるので、夏冷えを改善しつつぐっすり眠って、気持ちの良い朝を迎えられる可能性もあります。
睡眠をしっかりとる
一日の終わりである"睡眠"も大切です。適度な睡眠によって自律神経が安定し、夏冷えをはじめとする不調が起きにくくなります。
ここでポイントとなるのが、単に睡眠時間を確保すればよいわけではなく、"質の良い睡眠"をとる、ということです。
厚生労働省では、質の良い睡眠をとるために大切な要素として、以下の内容を挙げています。
【質の良い睡眠のために大切なこと】
- 日中はできるだけ日光を浴びる
- 就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見ない
- 部屋をできるだけ暗くして寝る
- 寝室は暑すぎず寒すぎない温度に保つ
- 就寝1~2時間前に体を温める
- できるだけ静かな環境で寝る
- リラックスできるパジャマ・寝具を使う
また、夏は暑くてなかなか寝付けない、あるいは途中で目が覚めてしまうこともあるでしょう。そういった場合は、冷感の寝具を使うなど工夫することもできます。冷房で室内を適温に保つことも大切ですが、冷房が強いと前述の通り、体を冷やしてしまいます。冷房を使うまでもないときは、夏用の寝具をはじめとした手段も検討していきたいですね。
参照元:『良い睡眠の概要(案)』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001151837.pdf
適度な運動を心がける
運動不足の方や、筋肉量の少ない方は、日々の生活に適度な運動を取り入れていくことをおすすめします。
とはいっても、いきなりハードな運動はなかなか継続しないものです。まずはストレッチやウオーキングなど、比較的簡単に始められて、負担の少ないものからチャレンジしてみてください。運動を習慣づけることで、筋肉が少しずつついていき、血行も促進されるので、冷えの解消につながります。
運動したあとは、体の冷えを防ぐために、汗を拭くことも忘れずに。
食事編
食生活も見直して、内側から夏冷えを防げる体を目指しましょう。
朝食をとる
体を適切な温かさに保つために、朝食は必須です。内臓は動くことで一定の熱をもちます。朝食をとって胃腸をはたらかせ、体の内側からの冷えを防ぎましょう。
特に、血流を促す働きのあるビタミンEや、体を温めてくれるたんぱく質が豊富に含まれている食品はおすすめです。たとえば、ナッツ類や卵、魚などが挙げられます。
逆に、控えたほうがよいのは添加物が多く含まれているものや甘い菓子パンなどです。添加物は腸内環境に悪影響を及ぼす可能性があるうえ、菓子パンを空腹の状態で食べると、血糖値が急上昇するおそれもあります。
急激に上がった血糖値を下げるためにはインスリンが大量に分泌されます。すると血糖値が急激に下がり低血糖を引き起こす場合もあります。血糖値の乱高下は自律神経の乱れを引き起こすことになるので、夏冷えをはじめとするさまざまな不調にもつながります。
冷え知らずの体をつくるには、朝食を毎日とるのは大前提として、血糖値を下げるはたらきのある食物繊維の多く含まれている食品がおすすめです。
朝食をとる際のポイントについては、こちらの記事もご覧ください。
自律神経を整えるには「朝」がカギ!更年期におすすめの朝食とは
飲食物の温度に気を配る
口にするものの温度にも気を付けましょう。
とはいえ、暑い夏に「冷たいものが欲しい」と思うのはごく当然のことなので、過度に我慢する必要はありません。冷たいものを"適度に"飲み食べするぐらいであれば問題ないでしょう。冷たいものそれ自体は適切な頻度・量で楽しみつつも、冷たすぎるものにお気を付けください。なお、体が冷えやすいのであれば、飲み物は常温にしてもよいかもしれません。
熱中症予防の観点からも、水分補給は必要です。「冷たいものは絶対にダメ」というわけではないので、適度にお楽しみください。
間食に気をつける

実は、冷たいものでなくとも、体を冷やす食べ物とそうでない食べ物があります。
水分の多い食べ物や、フルーツ、白砂糖、小麦は体を冷やします。同じ果物であっても、ドライフルーツは体を冷やしにくいのでおすすめです。特に、干し芋やレーズン、ショウガなどは東洋医学において体を温める働きがあるとされています。
上述したような体を冷やす食べ物の間食がいけないわけではありません。あくまでも、夏冷えを対策したいのであれば覚えておきたいというニュアンスです。
好きなものを無理に我慢しすぎる必要はないので、ご自身で取り入れられる範囲でドライフルーツの間食を少しずつ始めてみてください。
健康的な生活を送って、夏冷え知らずの日々を楽しもう
今回は、夏冷えの原因と対策方法をお伝えしました。
夏冷えには、体が外側から冷えてしまう場合と、内側から冷える場合とがあります。いずれにしても、冷房や冷たい飲食物による冷やしすぎは防いだうえで、健康的な生活を送ることが大切です。
本記事でご紹介した対策方法を取り入れて、健康で楽しい夏をお過ごしください。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
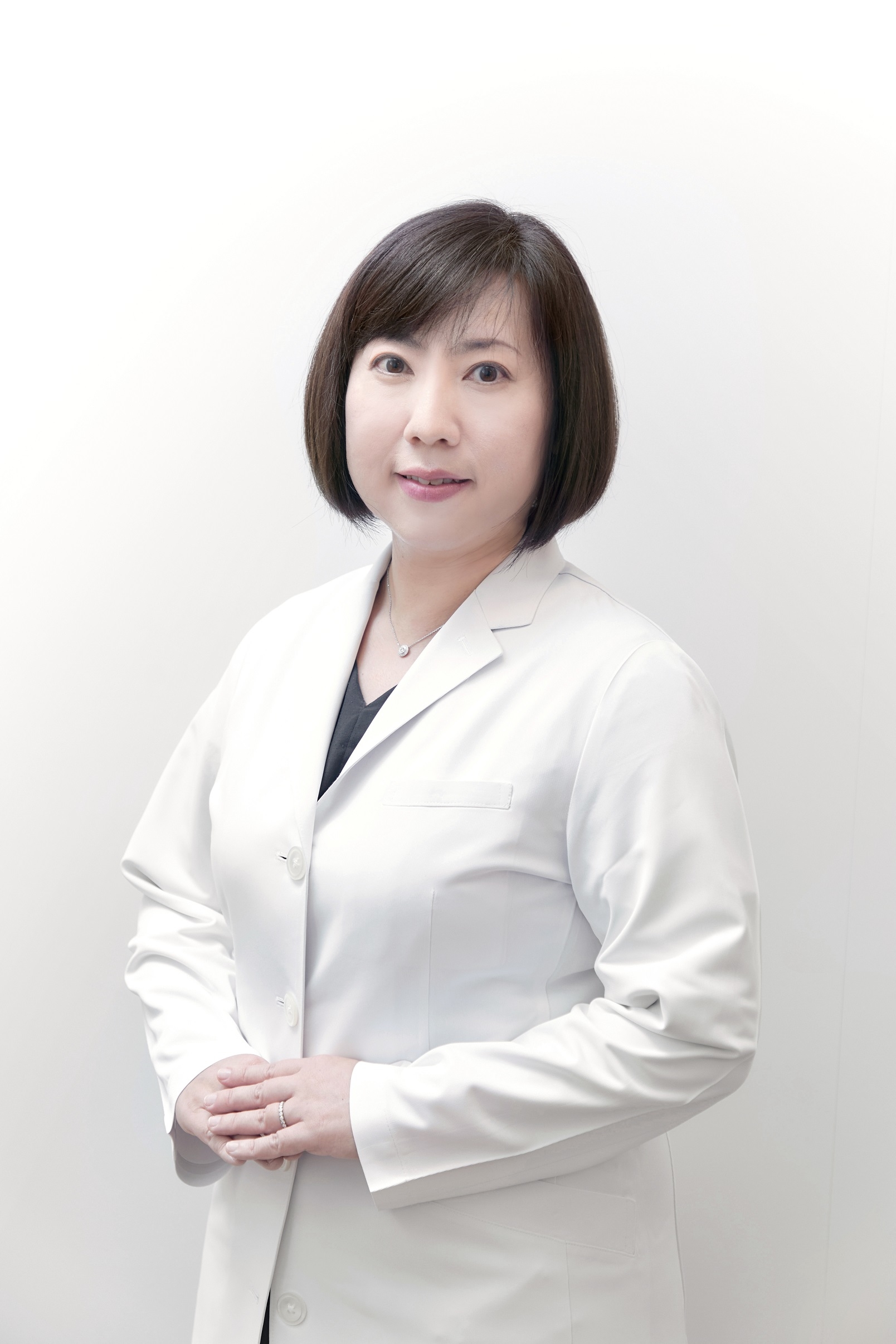
間瀬 有里(ませ ゆり)医師
医学博士
専門分野:婦人科
東京ミッドタウンクリニック、浜松町ハマサイトクリニックに勤務。日本医科大学医学部医学科卒業。日本産科婦人科学会専門医。日本産科婦人科学会指導医。日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医。東京ミッドタウンクリニックと同フロアでは、管理栄養士が常駐し、より健康でより美しい生活をサポートするためのヘルスケアショップ TMMC Plus(ティーエムエムシープラス)が展開。
東京ミッドタウンクリニック:https://www.tokyomidtown-mc.jp/
浜松町ハマサイトクリニック:https://www.hamasite-clinic.jp/
TMMC Plus(ティーエムエムシープラス):http://www.tmmcplus.com/
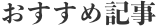 recommended
recommended
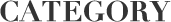 カテゴリー
カテゴリー