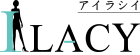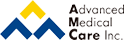更年期による頭痛とは?症状とともに原因や対処法を解説

閉経の前5年と後5年の計10年間を更年期とよびます。ホルモンの分泌が変動するため...
閉経の前5年と後5年の計10年間を更年期とよびます。ホルモンの分泌が変動するため、体と心にさまざまな不調が現れるようになります。
今回は、そんな更年期症状の一つである"頭痛"にフォーカスをあてて、原因や対処法を解説します。「頭痛を少しでも和らげたい」という更年期の方は、ぜひ最後までご覧ください。
更年期による頭痛の症状
頭痛は、痛みの原因やパターンによって、いくつかの種類に分けられます。なかでも更年期に多くみられるのが"片頭痛"と"緊張型頭痛"です。
また、くも膜下出血や脳腫瘍など他の疾患が原因で起こる"二次性頭痛"にも注意が必要です。
まず、これらの頭痛の各特徴を解説します。
片頭痛
"片頭痛"という名称はもともと、片側のこめかみあたりが痛むことに由来しますが、必ずしも片側だけが痛くなるわけではありません。実際には4割近くの方が両側性の頭痛を経験しています。以下に片頭痛の特徴を示します。
片頭痛の特徴
- 発作的に起こり、4~72時間持続する
- 片側(40%は両側性)が、ズキズキと脈打つように痛む
- 痛みの強さは中等度から重度で日常生活に支障をきたす
- 歩行や階段の昇り降りなどの日常的な動作により痛みが増す
- 光や音、臭いに敏感になる
- 吐き気や嘔吐を伴う
片頭痛には前兆を伴うタイプもあります。
最も多い前兆の症状は、キラキラした光や、ギザギザした光が視界に現れて見えづらくなる"閃輝暗点(せんきあんてん)"といった視覚症状です。他にも、チクチク感や感覚が鈍くなるといった感覚症状、言葉が出にくくなる言語症状などがあります。通常、前兆が5~60分続いた後に頭痛が始まります。
<こちらもCHECK>
こめかみがズキズキ痛む...女性ホルモンの影響による片頭痛への対処法
緊張型頭痛
緊張型頭痛の特徴を以下にまとめましたので、片頭痛と比較しながらご覧ください。
緊張型頭痛の特徴
- 30分~7日間持続する
- 通常両側性で、圧迫されるように、または締めつけられるように痛む
- 痛みの強さは軽度から中等度で、日常生活は可能ではある
- 日常的な動作で悪化しない
- 吐き気や嘔吐は伴わない
緊張型頭痛では、片頭痛と異なり、日常的な動作により痛みが悪化したり、吐き気を伴ったりすることはありません。また、片頭痛はこめかみあたりが痛むのに対して、緊張型頭痛は頭の全体に痛みが生じます。こうした痛みのパターンによって、どちらの頭痛に該当するのか見分けられます。
二次性頭痛
二次性頭痛は、なんらかの病気や頭部外傷などが原因で起こる危険な頭痛で、緊急対応を要します。くも膜下出血や脳梗塞、脳出血といった脳血管障害、脳腫瘍、髄膜炎などが該当します。
ある日突然頭痛の症状が出始めたり、初めてまたは今までと違う頭痛、徐々に悪化する頭痛、麻痺やしびれ・言葉のもつれ・発熱などを伴う頭痛を認めた場合には、意識障害がなくても速やかに受診することが大事です。
更年期に頭痛が起きる原因
更年期に起こりうる3つの頭痛の症状について、理解を深められたのではないでしょうか。
それを踏まえて以下では、更年期に頭痛が起きる原因を深掘りしていきます。
女性ホルモンのゆらぎ

更年期の女性では、女性ホルモンであるエストロゲンが変動を伴いながら低下していきます。片頭痛はこのエストロゲンの「ゆらぎ」が大きくなる際に悪化することが多く、逆に変動がみられなくなる閉経後には軽快します。
これは、エストロゲンの低下に伴う、セロトニンなどの脳内伝達物質の減少も頭痛に関与していると考えられています。また、エストロゲンの動脈硬化を予防する作用の低下は、血管障害のリスクを高め、二次性頭痛のリスクを高めます。
ストレスやメンタルの不調
上述したホルモン変動は、心にも様々な変化をもたらし、イライラや不安を感じやすくなることがあります。さらに更年期は、親の介護や子どもの自立など、社会におけるライフスタイルも大きく変わる時期でもあり、精神的ストレスも重なります。
こうしたストレスは片頭痛を悪化させたり、慢性的なストレスや緊張状態、肩こりが緊張型頭痛の原因となる可能性があります。
更年期の心に現れる症状
- 気分の落ち込み
- イライラ感
- 不安感
- 倦怠感
- 抑うつ感
- 集中力の低下
- 物忘れ
- 不眠
このような状況が続くと、心身が常に緊張状態となり、気づかぬうちに体もこわばりはじめます。そうして肩や首、背中の筋肉が緊張することで、緊張型頭痛を発症してしまいます。
更年期の頭痛への対処法
二次性頭痛を疑う場合は、直ちに医療機関への受診が必要です。また片頭痛や緊張型頭痛であっても、脳神経内科・外科や頭痛専門外来などの専門機関で診療を受けることが前提ですが、プラスアルファでできる対策や対処法をご紹介します。
漢方薬

漢方薬は、頭痛をはじめとする、更年期に現れるさまざまな症状に対して効果を発揮するといわれています。婦人科のクリニックや病院に相談して漢方薬を試してみるのも一案です。
以下は、更年期症状の緩和によく処方される漢方です。
| 種類 | 特徴 |
| 桂枝茯苓丸 (けいしぶくりょうがん) |
子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症など |
| 当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん) |
貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、不妊症、動悸、慢性腎炎など |
| 加味逍遙散 (かみしょうようさん) |
肩こり、疲れ、精神神経症状、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害など |
また、更年期の頭痛には以下の漢方薬が処方されることもあります。
| 種類 | 特徴 |
| 呉茱萸湯(ごしゅゆとう) | 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心 |
| 五苓散(ごれいさん) | 浮腫、ネフローゼ、二日酔、下痢、悪心、嘔吐、めまい、頭痛、糖尿病など |
| 釣藤散(ちょうとうさん) | 慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの |
※「ツムラ医療用漢方製剤一覧」より転載
<こちらもCHECK>
更年期の心と体の悩みにも◎「漢方」ってどう使うの?
更年期世代の心身のバランスはどう測る?漢方ならではの考え方
生活習慣の改善
適度な運動や睡眠、バランスのとれた食事にも気を配ることで、頭痛を含めた不調の改善が見込めます。
適度な運動習慣は、ストレスの軽減やリラックス効果、血行の促進をもたらし、頭痛の発症予防に有効です。ホルモンバランスを整える効果も期待でき、長時間のデスクワークの合間に軽いストレッチや体操を取り入れるだけでも効果があります。
逆に、過度の運動は頭痛を誘発する可能性があるため、ご自身の体調に合わせた適度な運動が重要です。脱水や低血糖にも注意しましょう。ウォーキングやヨガ、ピラティスなど、自分にあった運動をみつけ、定期的に取り入れてみてください。
適正な睡眠時間を確保することも欠かせません。成人では6時間~8時間の睡眠が適切と考えられています。起床後に日光を浴びて概日リズムを整えること、適度な運動を行うこと、過度の飲酒やカフェイン摂取を控えること、就寝前に明るい光やブルーライトを避けることなどにより、より質の良い睡眠を心がけましょう。
片頭痛の予防効果が期待される栄養素には、ビタミンB2やマグネシウムがあります。
ビタミンB2を多く含む食品にはレバーや鰻、魚肉ソーセージ、納豆、モロヘイヤ、卵、牛乳などがあり、マグネシウムを多く含む食品には豆類や藻類、種実類、干しエビなどの魚介類があります。これらはサプリメントで補ってもよいでしょう。
ナツシロギクやコエンザイム Q10などのサプリメントにも片頭痛の予防効果があることが知られています。
反対に、ハムやソーセージ、チーズ、ワインなどの過剰摂取は頭痛を悪化させる要因になります。また、日ごろから血糖の乱高下を避けた食生活を心がけることも大事です。
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法は、エストロゲンの「ゆらぎ」を緩和し、更年期の片頭痛への有効性が期待されますが、現時点でのエビデンスは乏しいです。逆に片頭痛が悪化することもあるので注意が必要となります。
頭痛以外の更年期症状を伴い、ホルモン補充療法が適切と判断された場合には、皮膚に貼る経皮吸収剤を選択した方が片頭痛を悪化させないとされます。
<こちらもCHECK>
医師が答える!更年期症状に◎なホルモン補充療法(HRT)のギモン
更年期は頭痛に悩まされやすい!早めの相談や適切な対処を
今回は、更年期に伴う頭痛の原因や対処法を解説しました。
更年期における頭痛のなかで、特に多くみられるのは片頭痛と緊張型頭痛です。
片頭痛は、加齢による女性ホルモンのゆらぎや、エストロゲンの低下に伴う脳内伝達物質の減少などが原因として考えられています。一方で、緊張型頭痛の原因は、ストレスや頭の周りをはじめ、肩や首、背中の緊張状態などが考えられています。
このような頭痛に対し、専門科での治療薬と共に行える対処法としては、漢方薬の服用、運動や食事などに気を配った健康的な生活が挙げられます。ご自身の症状や体調に合わせて、取り入れてみてください。
更年期のつらい頭痛を少しでも軽減して、毎日をあなたらしく過ごしましょう。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
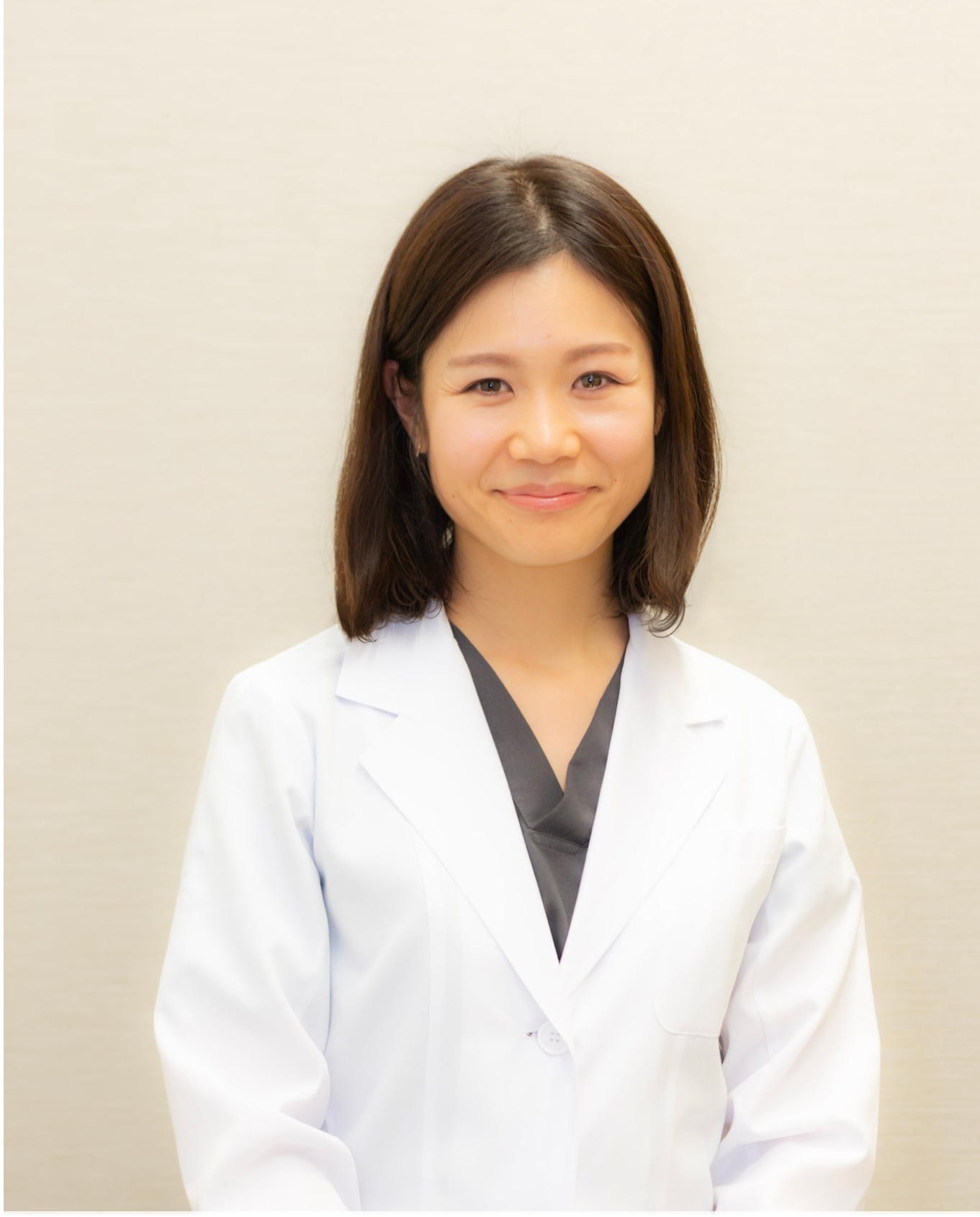
針金 永佳(はりがね えいか)医師
医学博士
専門分野:婦人科
東京ミッドタウンクリニックに勤務。日本医科大学医学部卒業。日本産科婦人科学会専門医。周産期新生児医学会周産期専門医。女性医学学会女性ヘルスケア専門医。新生児蘇生法「専門」コース修了。由利組合総合病院産婦人科、日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科・産科を経て現在に至る。
東京ミッドタウンクリニック:https://www.tokyomidtown-mc.jp/
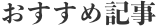 recommended
recommended
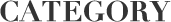 カテゴリー
カテゴリー