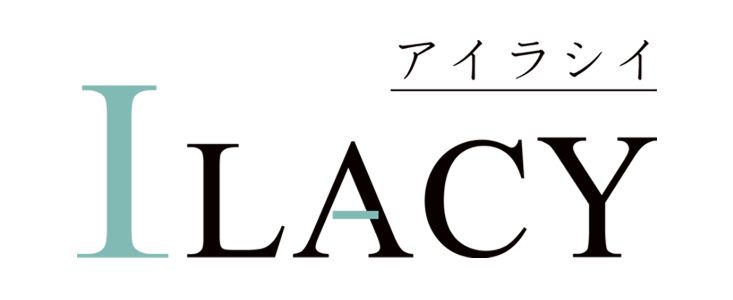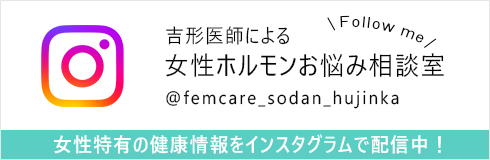【医師監修】更年期世代がピルをやめるタイミングや、HRT治療開始の目安


グランドハイメディック倶楽部 倶楽部ドクター
吉形 玲美(専門分野:婦人科)
生理不順や子宮内膜症、月経前症候群(PMS)の治療薬として注目を集めているピル。しかし、40歳を過ぎると処方してもらえない、いつまでピルを飲めばいいのかわからないといった声も多く聞かれます。今回は、ピルの服用を止めた結果、ホットフラッシュなどの症状に悩まされるようになった患者さんの症例を基に、更年期におけるピルの効果や、ピルからHRT(ホルモン補充療法)への切り替えタイミングについて、産婦人科医の吉形玲美先生に教えていただきました。
毎年10月18日は、更年期の健康にまつわる情報を世界に提供する日として定められた「世界メノポーズデー」です(メノポーズ=英語で「更年期」「閉経」のこと)。これを機に、今一度更年期や閉経に関する正しい情報を得て、人生の新たなフェーズを前向きに過ごしましょう。
※本記事は、2018年10月18日公開版を新たに校正・加筆をし、2025年版として更新したものです
【Case5】ピルからHRTによる治療へ――更年期世代の女性ホルモンとの付き合い方
O・Mさん(49歳)の場合
【おもな状況ヒアリング】
■一般的な閉経時期を迎え、ピルからHRTへの切り替えを検討
40代前半のころに月経不順で診療を受けた際、ピルを処方されました。まもなく50歳を迎えるにあたってHRTへの切り替えを検討していたところ、処方されていたピルが切れてしまい、飲まないでいた時期に初めてホットフラッシュのような症状が出たので相談しました。
■更年期症状の改善に有効な方法を知りたい
ホットフラッシュの症状の改善および、HRTに切り替えるタイミングを知りたいと思っています。
更年期症状に有効なピルの効果
――O・Mさんが月経不順で初めて受診した際は、どのような検査・診断をされたのですか。
最初は月経不順ということだったので、まずはホルモンの状態を見るための血液検査、子宮・卵巣の状態を見るための経腟超音波(経腟エコー)検査を行いました。こういった方の場合は、理想をいえば基礎体温をつけていただいていると、とても助かるんです。特に更年期を意識しはじめる40代以降で月経が乱れてきた方は、基礎体温表をつけていると体温の変化によって排卵のタイミングがわかるので、卵巣機能が保たれているか、また、生理がそろそろ来るかなども予測できるようになります。
そもそもホルモンの分泌量は毎日変わるものなのですが、それは閉経に近付くにつれて変動が激しくなるんです。なので、40代に入って、生理が不順になってきたという方は、基礎体温表をつけていただくだけでも状況の把握に役立ちます。O・Mさんの場合は、ホルモン検査からまだ閉経はまだ先の状態でしたので、初診後にHRT周期的投与にて低用量ピル内服時のようなサイクルをキープしつつ、症状改善をみていくことにしました。
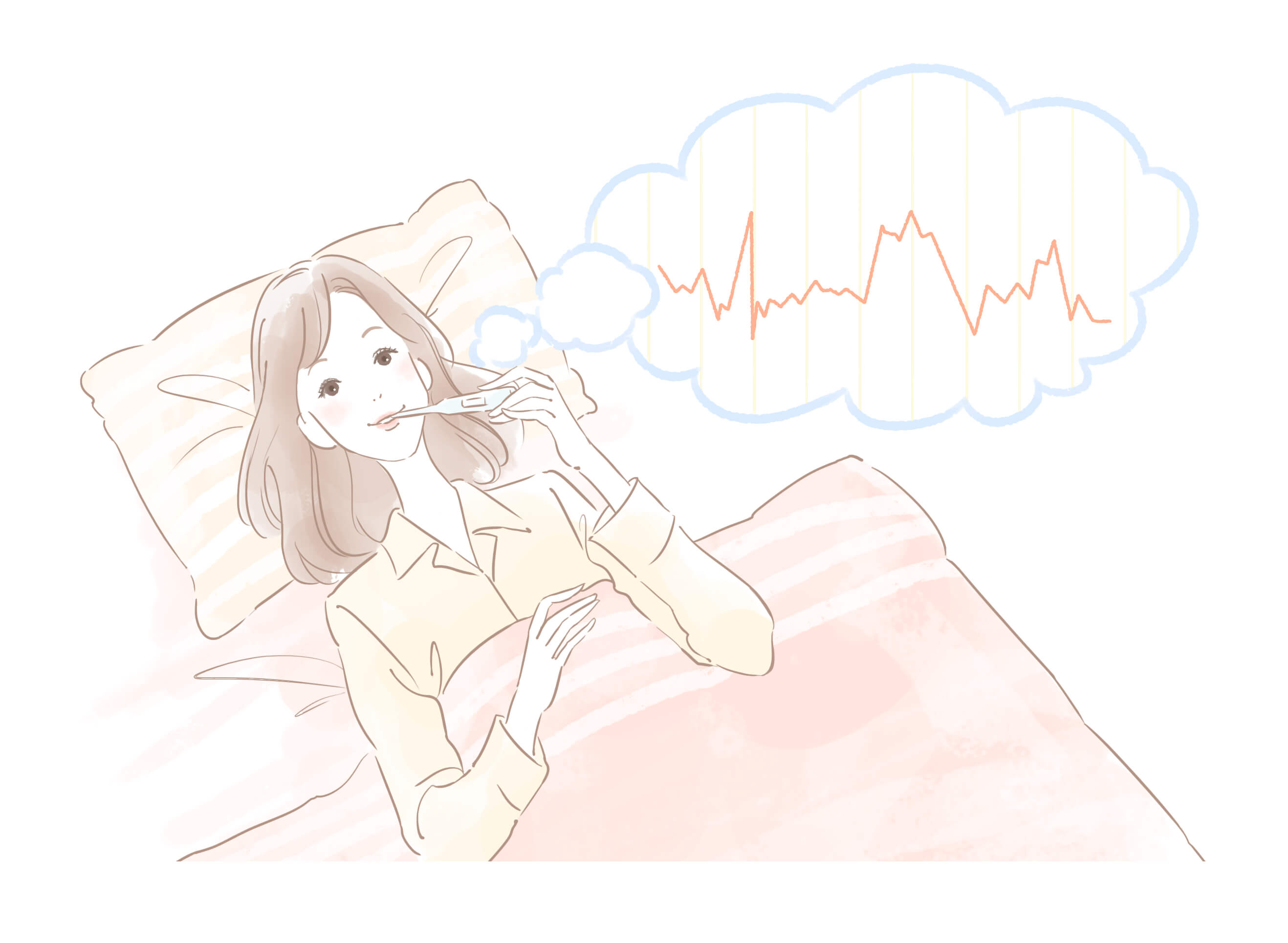
――生理不順に対して、ピルはどういった効果があるのでしょうか。
まず、ピルというのは、女性ホルモンの成分であるエストロゲンと黄体ホルモンの両方が含まれている薬で、排卵を抑える効果があります。それが女性の体に与える作用は2つあって、ひとつは卵巣から分泌しているホルモンの量を抑えること。これは、女性ホルモンの作用が強すぎるために生じる不具合、例えば月経困難症や子宮内膜症、PMSに代表される排卵後の体の不調など、それらを改善できるという効果があります。
そして、もうひとつの作用は、ホルモン量を安定させることです。更年期障害治療の場合、ピルを使うかHRTにするかの判断が難しいと思いますが、ピルにするひとつの目安となるのが、まだ卵巣機能が正常に保たれており、ご自身の体から女性ホルモンがある程度出ている方。先ほど申し上げたとおり、閉経が近づくとホルモン分泌量の波が激しくなるため、その波を穏やかに安定させることで症状が軽減されます。
<こちらもCHECK>
ピル服用時の注意と自分に合ったピルの見つけ方
――女性特有の症状にピルは有効であることはわかりましたが、最近は40歳以上の方にはピルを処方しないケースも多いと聞きました。それはなぜでしょうか。
一番は、ピルに含まれるエストロゲンによって、血栓症のリスクが高くなるからですね。そのリスクは年齢に比例して増えていくので、40歳以上の方には処方しない医療機関が増えているのはそのためです。
とはいえ、血栓症のリスクが高くなるのは、一般的には飲み始めの数ヵ月なんです。そのため、例えば若いころからピルを飲み続けている人で、状態が安定しているようでしたら、40歳になったからといってすぐにピルをやめなくても大丈夫だと思います。
ただ、飲んだり飲まなかったりというのはおすすめしません。一度やめたけどやっぱり飲もうとなると、そこからまた数ヵ月は血栓症のリスクが高まってしまうんです。したがって、ピルはPMSや月経痛対策が一般的です。飲み始めたら医師と相談の上、継続して飲むのがいいでしょう。

――ピルを飲んでいるあいだの診療パターンはどういった感じなのでしょうか。
通常は、初診で各種検査を行い、そこでピルを飲むことになったら、次は1ヵ月後に来院していただきます。そこで、検査結果とピルの服用状況を確認し、問題がなければその後はおよそ3ヵ月ごとに診察しています。3ヵ月ごとの診察では、症状が改善しているか、不正出血など気になる症状がないか、お薬が体に合っているかといったことを確認し、患者さんのお話を伺うのがメインですね。
――ピルを飲んで不正出血があったり、体に合わなかったりすることもあるのですか?
不正出血はホルモン剤の使い始めによく起こることなので、ピルの影響だと思っていいでしょう。ただ、一口にピルといっても、超低用量ピル、低用量ピル、中用量ピルと、さまざまな種類があります。また、含有されるエストロゲンと黄体ホルモンの組み合わせもピルによって異なるので、自分に合う薬を見つけることが大切。そういう意味では、患者さんに寄り添って、じっくり相談にのってくれる先生や婦人科を探すのが重要かもしれません。
自分に合ったピルが見つかると、月経痛や月経過多が改善されるほか、排卵が抑えられることでPMSなどの体の不調も良くなりますし、ホルモンの波を穏やかにしてくれるので、情緒が安定しないといった症状も抑えられる効果が期待できます。

ピルからHRTへの切り替えは50歳を目安に
――O・Mさんの場合、50歳を迎えるのを機にHRTへ切り替えることを検討されていましたが、一般的にピルからHRTに切り替えるタイミングはどういった時期なのでしょうか。
閉経の平均年齢は51歳頃といわれていますが、ピルを飲んでいる人はそのあいだに閉経を迎えるケースもあります。そして、ピルを使っていた目的が生理不順やPMSだった場合、閉経に入るとそれらがすべて解決する方もいらっしゃるんです。そのため、長年ピルを飲んでいる方も、50歳頃を目処に一度休薬してもらい、閉経に入っているかを確認します。閉経を迎えていて、ピルを休薬したままでも不具合のない方はHRTを行う必要はありません。
ただ、O・Mさんの場合は、ピルを飲むのをやめたらホットフラッシュのような症状が出たということなので、改めて治療法を見直すことにしたんです。O・Mさんが必要な女性ホルモンの量は、ピルではなくHRT世代に入っていたので、そのタイミングで切り替えることにしました。
<こちらもCHECK>
――O・MさんのようにHRTへの切り替えを検討しているという場合は、いつごろ相談に行けばいいのでしょうか。
50歳という年齢はひとつの目安になります。閉経を迎え、お薬がなくても更年期症状がなければそのままピルを卒業しておしまいですし、O・Mさんのようにホットフラッシュなどの症状が出る場合はHRTに移行するのが一般的です。HRTはピルに比べて女性ホルモンの含有量がぐっと減りますので、血栓症のリスクも下がりますから。とはいえ、個人差があるものなので、切り替えのタイミングはもちろん、薬の減らし方、やめ方、やめ時というのは、主治医の先生と相談しながら決めるようにしてください。
更年期にはどのような症状がみられるのか
本項からは、吉形先生のお話に関連して、更年期世代の女性が感じる不調についての情報をお届けしていきます。
更年期を迎えると、身体的にも精神的にも「なんだか調子が良くないな......」と感じることがあります。頭痛やほてり、憂うつ、不安などがみられ、日常生活に不都合が生じるケースも珍しくありません。
では、なぜ更年期にこうした不調を感じることがあるのでしょうか。主な理由は、加齢に伴って女性ホルモンがゆらぎ、自律神経のバランスが乱れるためです。自律神経の状態を正常に保つことは、心身の健康を守るうえで欠かせないため、そのはたらきが乱れると不調を感じてしまうのです。
更年期を迎えると生理にどのような変化がみられる?
女性ホルモンの分泌量は、40歳を過ぎた頃から増減を繰り返しながらゆらぎ、閉経後に急激に減少します。更年期では、このゆらぎによって生理にさまざまな変化が起こる場合もあります。
その具体的な変化にはどのようなものがあるのかを、以下で確認していきましょう。
周期が乱れる
更年期に起こりうる生理の変化としてまず挙げられるのが、生理周期の乱れです。周期が短くなる"頻発月経"とよばれる状態になる、あるいは無月経の状態が続くなど、次の生理がくるまでの期間がわからなくなるのが特徴です。生理周期の正常な範囲は25~38日とされていますが、この期間より7日以上の変動が続く場合は、生理不順が起きているといえます。
また、周期が「2か月に1回」「3か月に1回」といった具合に延び、最後の生理から1年が経過しても次の生理がこない場合は、閉経とみなされます。
生理期間が変わる
生理期間が変わる可能性があることも、更年期における生理の特徴です。
年齢を重ねると、生理が8日以上続く"過長月経"や、反対に生理が2日以内で終わる"過短月経"になることがあります。こうした期間の変化は、加齢に伴う卵巣機能の低下によってホルモンバランスが乱れ、子宮内膜が周期的にはがれなくなることが原因と考えられています。
ただし、過長月経や過短月経は、子宮の病気が関係していることもありますので、「更年期だから」とご自身で判断せずに、一度婦人科で相談するとよいでしょう。
経血の量が変わる
更年期を迎えて女性ホルモンの分泌量が減少すると、経血量が過度に多くなる"過多月経"が起こりえます。
これは、1回の生理における経血量が150mL以上になる状態のことで、ナプキンやタンポンを短時間で交換しないと漏れてしまうケースもあります。また、夜用のナプキンを使用していても対処が難しい、あるいはレバー状の塊が出るといった症状がみられ、日常生活にも支障をきたしかねません。放置すると、重度の貧血によって不整脈や、腎機能の低下などを引き起こすリスクもあるため、違和感を覚えたら医師に相談することをおすすめします。
また反対に、経血量は少ないものの、2~3週間にわたって出血が続く場合も注意が必要です。細菌が増殖して、さまざまなトラブルにつながる可能性があるので、少しでも気になる症状がある際には、早めに婦人科を受診することが大切です。
不正出血が起こる
不正出血も、更年期にみられる生理の変化の一つです。
この時期にみられる不正出血は、単なるホルモンバランスの乱れではなく、子宮頸がんや子宮体がんのような疾患が原因となる場合もあります。閉経後早期(数年程度)であれば、機能性出血がみられることもあります。
生理期間や経血量が変化し始めると、出血が更年期によるものなのか、それとも病気のサインなのかを適切に判断するのは難しくなります。「更年期による変化だから大丈夫」と自己判断はせず、出血が長引く、また頻繁に出血するときは婦人科の受診をご検討ください。
生理の変化に隠れている可能性がある病気
更年期における生理の変化は、なんらかの病気が原因となる可能性もあります。ここでは、生理のトラブルを引き起こす代表的な病気を紹介します。
子宮筋腫
閉経前の女性なら誰もが発症する可能性があるのが、子宮筋腫です。
子宮筋腫は、子宮壁(筋層)に発生する良性の腫瘍で、できる場所や大きさ、数によって自覚症状の有無が異なります。たとえば、子宮の外側に腫瘍ができた場合は生理の変化が出にくく、腫瘍が大きくなるまで自覚症状はあまりありません。
自覚がないまま腫瘍が大きくなると、圧迫により排尿・排便がしづらいなどの症状が起こるケースも出てきます。子宮の内側に腫瘍ができた場合は、経血量の増加をきたしやすく、重度の貧血になる場合もあります。日常生活に支障をきたす状態になっているときには、薬物療法や手術により治療を行います。
なお、子宮筋腫を発症していても数センチ以内と小さく、無症状であれば、治療はせずに経過を見るのが一般的です
子宮内膜症
生理がくるたびに下腹部の痛みが増す場合は、子宮内膜症を発症しているかもしれません。
子宮内膜症とは、生理の際にはがれ落ちるはずの子宮内膜の組織が、卵巣や卵管などで増殖してしまう病気です。病状は生理を重ねるごとに悪化し、下腹部や腰、骨盤の痛みが慢性化することもあります。
子宮内膜症が起こる場所はさまざまですが、なかでも卵巣内で発症した場合は注意が必要です。本来、子宮の内側にあるべき子宮内膜の組織が卵巣に入り込むと、排出されなかった古い血液が溜まって嚢胞を形成します。これは"チョコレート嚢胞"とよばれ、卵巣がんのリスクを高めるとされています。
そのため、激しい生理痛・生理以外の時期の下腹部痛など、子宮内膜症が疑われる症状がみられたら、早めに婦人科を受診するのが重要です。
子宮頸がん
子宮頸がんとは、子宮の入り口にできるがんで、主な原因は性交渉によるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染です。
HPVは、性交渉を経験した女性の多くが感染する可能性のあるウイルスです。一般的には、感染しても自然に消滅するとされており、必ずしもがんに進行するわけではありません。しかし、0.15%ほどの割合ですが、数年かけてがん化するケースもあります。
子宮頸がんの初期段階では、自覚症状がないことがほとんどです。がんが進行するにつれて、不正出血、おりものの変化といった症状がみられるようになります。
子宮頸がんは進行スピードが比較的速いため、早期に発見できるよう定期的に検査を受けたいところです。
子宮体がん
子宮の入り口を除いた上部3分の2の部分に発生するがんを、子宮体がんといいます。更年期と重なる年代の女性に多くみられるのが特徴です。
年齢を重ねると発症のリスクが高まるのは、閉経によって女性ホルモンであるエストロゲンと、プロゲステロンのバランスが崩れてしまうためです。閉経を迎えて排卵が行われなくなると、子宮内膜を増殖させるエストロゲンと、それを抑制するプロゲステロンの分泌量が減少します。このうちプロゲステロンの分泌量が急激に減少するため、エストロゲンの作用を受けやすい状態になってしまうのです。その影響で子宮内膜が異常に増殖し、子宮体がんのリスクになると考えられています。肥満や極端な生理不順もリスクになります。
子宮体がんで多くみられるのは、閉経後の不正出血です。閉経前では、極端な生理不順や無月経の場合、注意が必要です。
無症状の場合は、一般的には定期的に検査を受ける必要はありません。ただし、家族に子宮体がんに罹患した経験のある方がいる場合や、気になる症状がある場合は、一度婦人科医師に診てもらうと安心です。
更年期を迎えると生理も変化する!気になる症状が表れたら早めに受診しよう
今回は、吉形玲美先生にピルからHRTに切り替えるタイミングをお伺いしたのち、更年期にみられる生理の変化をお伝えしました。
更年期を迎えると、女性ホルモンのゆらぎによって自律神経のバランスが乱れ、心身にさまざまな不調が表れることがあります。生理にも影響をもたらし、周期が不安定になる、あるいは経血量が増えるといった変化がみられるケースも少なくありません。
ただし、こうした生理の変化は、更年期によるホルモンバランスの乱れだけに限らず、病気が原因で起きている可能性も考えられます。気になる症状が表れた際には、自己判断はせずに婦人科を受診することをおすすめします。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人


吉形 玲美 (よしかたれみ) 医師
医学博士/日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
専門分野:婦人科
産婦人科医として医療の最前線に立ち、婦人科腫瘍手術等を手掛ける傍ら、女性医療・更年期医療の様々な臨床研究にも数多く携わる。女性予防医療を広めたいという思いから、2010年より浜松町ハマサイトクリニックに院長として着任。現在は婦人科専門医として診療のほか、多施設で予防医療研究に従事。更年期、妊活、生理不順など、ゆらぎやすい女性の身体のホルモンマネージメントを得意とする。
2022年7月「40代から始めよう!閉経マネジメント」(講談社刊)を上梓。
2023年9月より「日本更年期と加齢のヘルスケア学会」副理事長に就任。
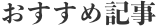 recommended
recommended
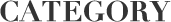 カテゴリー
カテゴリー